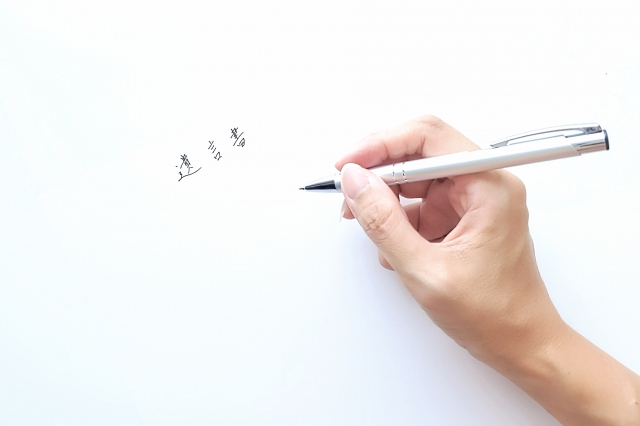遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の残した遺産(相続財産)を、誰が・どのように・どれくらい受け取るかを、相続人全員で話し合って決める手続きのことです。
この協議は、遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員が合意して異なる分け方をしたい場合に必要となります。
協議の進め方と成立条件
1. 協議が必要なケース
被相続人が遺言書を残していない場合、または遺言書で特定の財産の処分方法が指定されていなかった場合に、遺産分割協議が必要になります。
2. 相続人・相続財産の確定
協議を始める前に、以下の準備が必要です。
- 相続人の確定: 戸籍謄本などを収集し、誰が相続人であるかを確定させます。一人でも欠けると協議は無効になります。
- 相続財産の確定: 不動産、預貯金、株式などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産すべてを調査し、財産目録を作成します。
3. 全員参加の原則と合意
遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が絶対条件です。
- 欠席は不可: 相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所が選任した特別代理人が参加します。
- 全員の合意: 法定相続分にとらわれず、全員が納得すればどのような分け方(例えば、長男が不動産を全て相続し、他の相続人が金銭を一切受け取らないなど)も可能です。
4. 遺産分割協議書の作成と効力
話し合いがまとまったら、その内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
| 項目 | 詳細 |
| 記載内容 | どの財産を、誰が、どれくらいの割合で相続するかを明確に記載します。 |
| 署名・押印 | 相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。 |
| 添付書類 | 相続人全員の印鑑証明書を添付します。 |
| 効力 | この書類は、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約・名義変更などの各種手続きにおいて、必須となる重要書類です。 |
協議がまとまらない場合
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での手続きに移行します。
1. 遺産分割調停
- 申立て: 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
- 内容: 裁判官と調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を聞きながら、円満な解決を目指して話し合いを進めます。
2. 遺産分割審判
- 移行: 調停でも合意に至らなかった場合、遺産分割審判に移行します。
- 内容: 裁判官が、法律に基づいて、客観的な証拠や事情を考慮し、強制的に遺産の分割方法を決定します。相続人はこの審判結果に従うことになります。
遺産分割協議のメリット・注意点
メリット
- 自由度が高い: 法定相続分にとらわれず、柔軟に財産を分けることができます。
- 実情に合わせた分割: 特定の相続人が被相続人の介護に貢献していた(寄与分)り、生前に贈与を受けていた(特別受益)などの実情を反映させやすいです。
注意点
- 期限: 法律上の期限はありませんが、相続税の申告・納税期限(相続開始から10ヶ月以内)相続登記(亡くなってから3年後の年度末)があるため、それまでに協議を終えるのが理想です。
- 全員の同意: 一人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、手続きが先に進められなくなります。
- 名義変更: 協議書がないと、不動産や預貯金の名義変更ができません。